
1960年代製のIWC「オールドインター」の実力にひれ伏す
2020年7月、同僚であり友人でもある国産時計コレクターOさんが、百貨店の催会で手持ちの初代グランドセイコー2本を理想的な状態の初代GSと交換取引したという話を聞いて、古い時計も良いよねと触発された。
では、なぜオールドインター(IWC)にしたのかというと、和田将治さん(HODINKEE Japan)がブロガー時代に書かれたCal.89(手巻きムーブメントの傑作機)のレビューを読んで、改めてヴィンテージウォッチの良さを味わいたいと心から思ったからだ。
[su_content_slide][/su_content_slide]僕は過去2回のヴィンテージウォッチの収集(いずれも50年代製金無垢のIWCとオーデマ・ピゲ)で痛い目を見ていることもあり、ビンテージウォッチは専門店で購入すると決めている。森下に本店を構えて、僕も何度かお邪魔させてもらったケアーズ、銀座のシェルマン、あと最近HODINKEE Japanのインタビューで知った江口時計店のストックリストを眺めて出物を待つのだ。
ここに挙げた専門店は、ストックリストに良いものが挙がるとすぐに売れてしまうので、これはと思うものはすでにHold(取り置き中)かSold(販売済み)になってしまうことも多々あり、これまで何度地団駄を踏んだか数えきれないほどだ。
僕のヴィンテージウォッチの収集基準は、1960年代製であることに尽きる。思えばこの時代が腕時計の絶頂期であったと思われ、外装面はともかく、内部のムーブメントの完成度と耐久性、部品のストックも現在まで豊富に存在するモデルも多い。オメガの30mmキャリバーは少し時代は遡る(’50年代)ものの、その好例である。つまり、僕は現在においても日常使いできる点を重視している。これが50年代や70年代製となると、とたんに維持に手間とお金がかかる。また、この時代の時計はとにかくケースが小さいのがありがたい。
[su_photo_panel shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” radius=”10″ photo=”https://koichiiwahashi.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG_3738.jpg” alt=”IWC Ref.810A”]IWC Ref.810A 針の夜光に劣化が見られる以外は、シミひとつない状態の良いダイアル[/su_photo_panel]僕が購入した個体はやはり1960年代後半製造のIWC Ref.810A。センターセコンドの3針でカレンダーはない。搭載するムーブメントはハック機能のついた自動巻ムーブメントCal.854。Hodinkeeのビンテージ販売サイトでも全く同じモデルが$2,500でSoldされたが、僕の個体はケアーズ ミッドタウン東京店で販売されたものだ。
[su_content_slide][/su_content_slide]文字盤にはシミもなく、ややクリーム色に焼けたシルバーダイヤル。針とアプライドインデックスには寿命の尽きたトリチウムのルーム(蓄光塗料)が残されている。針の形状はロイヤルオークと同じバトン型の、如何にもドレスウォッチ然としたものだ。
ケースサイズは35mmに届かないほどのサイズで、ラグ幅は18mmだ。現行のIWCにはお目にかかれないサイズだが、僕の細い手首(15.5cm)には実に程よい。厚みは11mmと決して薄型とは言えないものの、その半分近くはドーム型のプレキシ(プラスチック)風防に占められているので、ケースデザインそのものは実にスマートだ。
精度については、正直言ってあまり期待はしていなかったものの、実際に着用した携帯精度は日差+3秒という「現行ロレックスかよ」と突っ込みたくなるような優秀さで、これには舌を巻いた。この時計に搭載されるムーブメントは、Cal.854でいわゆるぺラトン式自動巻を採用した自社製自動巻85系と呼ばれるムーブメントの後期型である。Bが末尾に付くものはハック機能(秒針停止機能)を示すというのが通説であるが、ないものでもハック機能が搭載されていたりと判然としない。
ここでぺラトン式自動巻に触れておくと、これはIWCのエンジニアであったアルバート・ぺラトンが発明した両方向自動巻機構を指す。自動巻というのは、ムーブメント上部に取り付けられたローターが回転することによって、主ゼンマイに動力が蓄積される仕組みである。ところが、そのローターは時計回りにも反時計回りにも回転するわけなので、片方のみの回転から動力を伝えるのでは、不十分なのである。そこで、各社両方向自動巻機構の開発にシノギを削った。現在は、リバーサーと呼ばれる切替車(歯車)を使った方式を採用するメーカーが多く、高級機でも例えばオーデマ・ピゲはCODE11.59やロイヤルオーク15500STに搭載するCal.4302を従来型のスイッチングロッカー式ではなく、リバーサー式に切り替えた。リバーサー式は自動巻機構の黎明期から存在していたものの、素材工学が未熟だった当時では部品の摩耗が激しく、切替車の交換がオーバーホール時には必須だったと思われる。
ぺラトン自動巻は、歯車だけで構成されるリバーサー式が抱える部品の摩耗を軽減するために、ローターに楕円形のカムを取り付け、カタツムリの目玉のようなベリリウム鋼ベアリングの、目と目の間を左右に押し上/下げることで、香箱のホイールを2本の爪が一定方向に整流しながら制動する。 一方向にしか回転しないよう歯止めに接続された歯のあるホイールとラックで成る2本の爪が巻き上げる方式をラチェット式と呼ぶが、ぺラトンの場合、この構造がかなりシンプル化されているのだ。
このぺラトン自動巻の効用は、上述した部品摩耗の低減の他に、巻上げ効率に優れる点にある。ムーブメントが停止している状態からリューズで手巻きせずとも、少し回すだけで即座に運針を開始する点はセイコーのマジックレバーに非常によく似ている。ただし、欠点はローターが回転しても巻上げが発生しない不動差角が大きいため、重いローターを乗せる必要があったことだ(上述した高い巻き上げ効率は、巻き上げが有効になって初めて実現する)。実用時計としてローターに比重の重い貴金属を用いることが許されなかったIWCのぺラトン自動巻機構は、体積の大きいステンレス製ローターを用いらざるを得ず、薄型化というトレンドに応えることができなかったため、クォーツショックによってついに潰えてしまったのである。しかし、近年IWCはこのぺラトン自動巻上機構を自社のアイデンティティ―として見直しており、セラミック技術とともにブラッシュアップした現行自社製ムーブメントCal.82220に採用している(ポルトギーゼなど)。現行のIWCはケース径40mm超が主流なので、ぺラトン自動巻ムーブメントの採用は合理的といえる。
[su_photo_panel shadow=”0px 1px 2px #eeeeee” radius=”10″ photo=”https://koichiiwahashi.com/wp-content/uploads/2020/09/IMG_3740.jpg” alt=”IWC Ref.810A”]魚マークの入ったリューズは防水ケースの証[/su_photo_panel]2020年新作のポルトギーゼ・オートマティック40を私も試着したが、大型ケースの多いIWCのラインアップの中では腕周り15.5㎝の僕の腕の収まりは抜群だった。また、クロコストラップの3サイズから選択できるので自分の腕のサイズにフィットした選択ができる(ジャガールクルトなどリシュモン系列のブランドはレザーストラップにいくつかのサイズを用意しているようだ)。とはいえ、現行機に35mmを求めることはできない。やはりここにヴィンテージを選ぶ必然性が僕にはあった。
[su_content_slide][/su_content_slide]巻上げ効率の良さによるエネルギー伝達の安定性に加え、姿勢差による誤差に強いといわれるブレゲ巻き上げヒゲゼンマイを採用しており、テンワには2対のマスロット偏心錘が付き、ウェイトの制御が可能だ。ヒゲゼンマイの自由運動を可能とするフリースプラングではないものの、微動緩急装置が備えられている。当時のロレックス Ref.1530に匹敵するムーブメントであったのではないだろうか。なお、Ref.1530はリバーサー式のムーブメントであり、アルマイト硬化処理されたアルミニウム製のリバーシングギアを採用し、軽量化と摩耗対策が施された傑作ムーブメントである。アルミニウムといえば、IWC 85系後期型(853/8531/854(B)/8541(B))の香箱にも採用されているが、航空機産業における普及が背景にあったのではないだろうか。
当時、この85系のムーブメントCal.8531を搭載したRef.648A(通称“寄り目”)の1960年代前半の小売価格は92,800円だった。1960年代を通じて大学初任給は倍以上に跳ね上がったので一概には比較できないが、1965年の大学初任給が21,600円であったことを考えると、4か月分超である。1960年に発売された初代グランドセイコーの小売価格が25,000円であることを考えると、舶来時計として格式も段違いに上だったのだろう。余談であるが、当時のブラウン管カラーテレビ(1960.9.10よりカラー放送開始)と国産車は同じくらいの価格で、およそ30万円であった。
この時計が60年近くの時を経て、未だに高精度を保ちながら動くのも然ることながら、オーバーホールが継続できるほど部品ストックが存在する事実にも驚かされる。基本的にどんな時計もメーカーが生産を終えてしまえば、部品の供給も停止してしまうためオーバーホールすることができなくなる。部品は自作することも可能であるが、コストに見合うものではない。したがって、部品を流用するためのドナーとなる時計が必要となり、そのためには一定の流通量が確保されている前提条件が揃わなければならない。オールドインターは、そうした所与の条件に恵まれているため、時計そのものを入手するためのコストも比較的手ごろで、状態が良いものでも20万円を超えることは少ないのではないかと思う。とはいえ、重いローターを積む85系ムーブメントは、ローター芯が頑丈に作られているものの、経年劣化による損傷を受けていないか確認が必要だ(シンプルに時計を振ってローターが裏蓋に干渉するような音がしないかがポイントとなる)。
今日は出社。まだまだナツいですね〜 pic.twitter.com/uldTNMgcmY
— イワシ@腕周り16.5cm (@Iwaxasky) August 27, 2020
ただし、この時代のオールドインターも防水性能が向上したスポーティウォッチであるYACHT CLUB(ヨットクラブ)やINGENIEUR(インヂュニア)に関しては人気が高く、価格も手ごろとは言い難くなっている。ヴィンテージにはあまり入れ込み過ぎないというのが僕の持論なので、余程潤沢に資金があったとしても、あまりお勧めしない。
僕はダイヤルもケースも、そしてムーブメントも極めて良好な個体を選ぶことができたが、惜しいのはオリジナルの尾錠が付いていないことだった。方々を当たって60年代のフィッシュアイ(魚眼)マークのついたオリジナル尾錠を入手することが叶った。しかし、尾錠だけでかなり高価だったことに加え、尾錠幅が15mmとレディメイドのベルトでは対応が難しい。何とか尾錠幅16mmのクロコダイルベルトに収まっているが、今後はラグ幅18mm-尾錠幅15mmのオーダーメイドでベルトを調達する必要がある。しかし、尾錠と時計本体の時代考証性はヴィンテージウォッチを楽しむひとつの醍醐味だと僕は考えるので、これはこれでよかったと考えている。願わくは、フラットなリザード革のベルトを合わせたいと考えている。
とはいえ、ヴィンテージウォッチが僕の日常で登場する機会はそれほどないだろう。僕は、現行型を日常の時計として愛用しているので、このオールドインターを楽しむ機会は、日常用の時計がメンテナンスで手元を離れているときだけと想定している。ただ、手元を離れる2,3カ月の間は稼働してもらわないと困るわけだ。日常使いできるほどの耐久性を僕がヴィンテージウォッチに求めるのは、そのためだ。
ヴィンテージウォッチの中で、オールドインターはオメガの30mmキャリバーと並び王道といえる存在だと思う。日常使いでき、精度に優れ、手ごろな価格で入手でき、メンテナンス性に優れる。何よりも時計そのものが60年近くも生き残ってきた証といえる存在なのだ。この事実だけでも驚異的な存在といえよう。今はたまたま僕の手元にあるが、大切に扱い次の若い世代の時計愛好家にバトンタッチできることを願ってやまない。





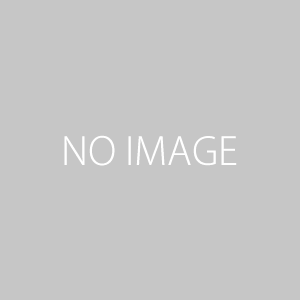





この記事へのコメントはありません。