
大岡昇平・著『レイテ戦記』の物量感に圧倒されました。
太平洋戦争の天王山と言われたフィリピン・レイテ島を巡る日米の戦いを克明に描いた『レイテ戦記』上・中・下巻を2月下旬に3日間かけて読み終えました。
いや〜疲れました。
第二次世界大戦を描いた書籍としては森村誠一の『悪魔の飽食』シリーズを読んだことがありますが、あちらは後方部隊の残虐的な人体実験をやや政治的バイアスがかった筆致で読者を誘導する印象を受けたのですが、本書は克明な日米両政府文献による取材に基づき、残虐な描写も淡々と語る(もしくは取材対象者の帰還者に語らせる)ようなスタイルですね。
筆者自信がミンドロ島で米軍の捕虜になっていることから、リアリティが半端じゃないのです。 この本の多くを占める兵站や配備に関する記述は国家間の「戦争という事業」の物量感を嫌という程見せつけてきます。
戦記に詳しい専門家はここからも何がしかを読み取るのでしょうが、僕は「物量感」として解釈しました。同時に、この物量感はディティールの精密さと相まってリアリティと切迫感を物語に与えるのです。
大岡自身によると、この本は「戦争文学」ではなく「小説」に分類されるようで、少し驚きました。これほどの精密な記録はノンフィクションか第1級の史料として扱っても良いと思えたほどです。
ところが、読み進めていくと、大岡のダークサイドとも言える感情の爆発が垣間見えたりするのです。例えば、このような表現です。
フィリピン人はこれらの損失を、白い天使 アメリカ人に猿のような日本人を追い払ってもらうために堪えた
日本人である大岡がわざわざフィリピン人をして「猿のような」と語らせることに、非常に屈折した感情と絶望感を覚えました。大岡が白人に対する強烈な劣等意識を持っていた証左でしょう。
知識人がこの体たらくなので、現代の日本人が欧米人に強く出られないのは仕方のないことかもしれません。
ところで、レイテ戦で初めて出現した特攻という戦術に対して、司令部の外道性は糾弾しつつも死に臨む搭乗員に美を感じるところは、大岡の文学者としての感性なのでしょうか?あるいは憐憫に過ぎないのか?
特攻に関する記述は小林よしのり『戦争論』に多く引用されていたので、本書からかなり影響を受けていますね。 興味深いのは次の行です。これは戦場に赴いた人間でないと知り得ないことでしょう。
兵隊の中には神経の鈍い、犯罪的傾向を持った者がいた。石のように冷たい神経と破壊欲が、あくまでも機関銃の狙いを狂わせないこともあった。与えられた務めを果たさないと気持の悪い律儀なたちの人間も頑強であった。普段はおとなしい奴と思われ、大きな声でものをいわない人間が、不意に大きな声を出して、僚友をはげましたりした。
レイテ戦は日本側に8万以上の戦死者をもたらした一方、米軍側は3,500人でした。日本軍はほぼ全滅と言っていいでしょう。米軍の損害も結構なものですが、拮抗していたとはとても言えません(ノルマンディー上陸作戦の連合国側とドイツの戦死傷者はほぼ同数)。
敗軍からは次第に遊兵になる者も現れて、乞食同然に成り下がるのです。そして食物を断たれた兵士の間で「人肉食」の噂まで出るのです。この人肉食のエピソードについては取材対象者の口が重く、確たる証言は得られなかったそうです。
とにかく、膨大なデータの羅列は戦争における物量感をまざまざと見せつけるという点で、非常にリアリティを感じさせられました。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。



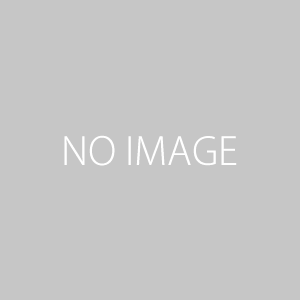

この記事へのコメントはありません。