
『戦後経済史』私たちはどこで間違えたのか 野口悠紀雄 著(東洋経済新報社)のソフトな語り口にシビれる
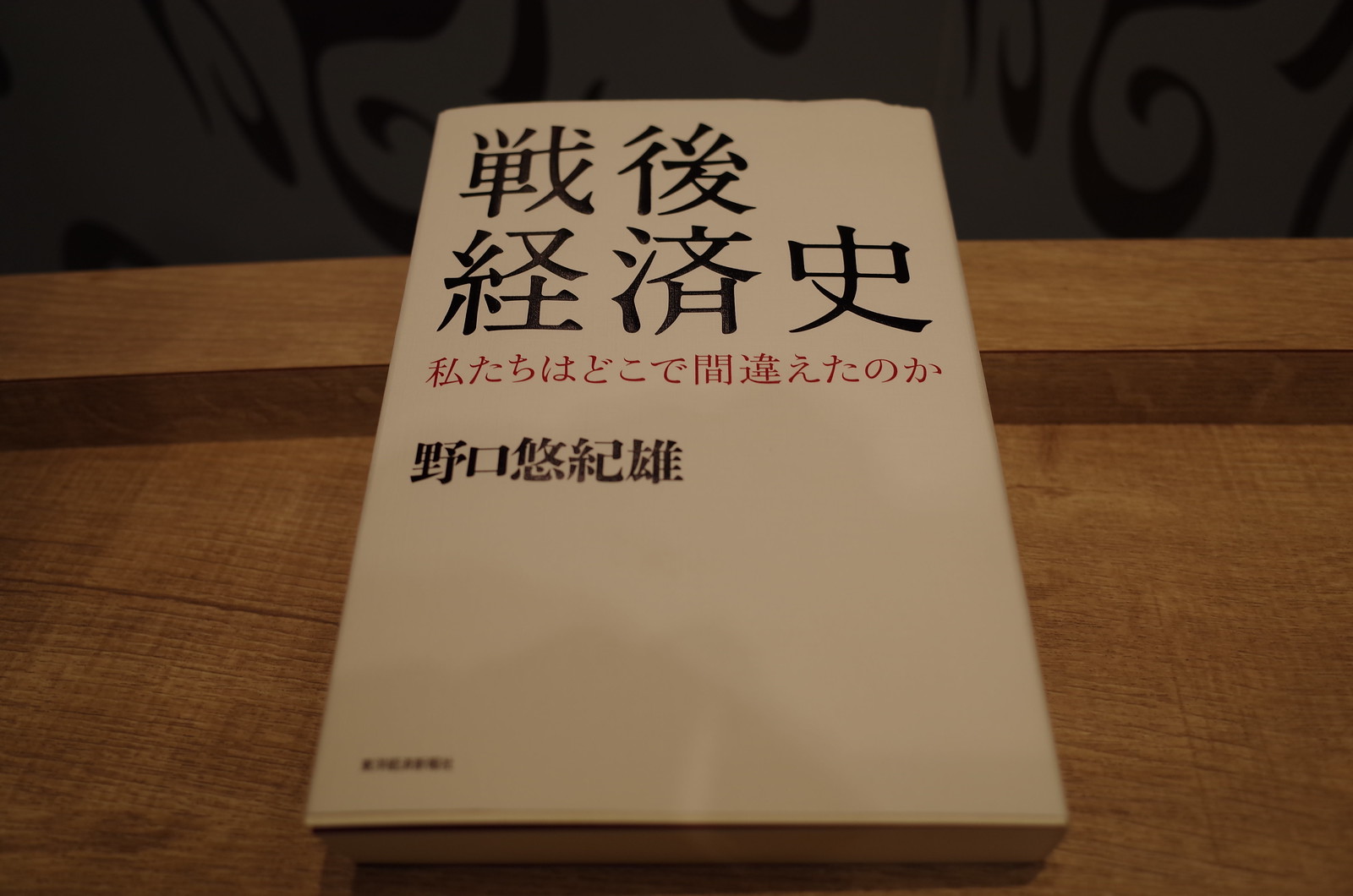
僕は経済学者の野口悠紀雄氏を非常に尊敬しています。僕のブログ初期の語り口は野口氏の東洋経済の連載の影響を色濃く受けた(マネをした)ものです。彼は学者なのでいいですが、僕の場合独りよがりになってしまい今読むとキモチわるいので、止めましたが。
そんな野口氏の新著を今更ながら読んでみました(仕事帰りにカフェで4時間かけて読了)。
で、『戦後経済史』の語り口を読んでひっくり返るほど驚きました。とても優しい語り口なんです。普段の「その理由を企業法人統計のデータを使って次に敷衍しよう」みたいな難解なフレーズがないんです。 これじゃあ、池上彰じゃあないですか教授…
日本戦後経済史でもあり回顧録でもある本書
著者の日本政府に対する怨嗟は東京大空襲で国が市民を守らなかったという原体験にあるようです。著者が政府や中央銀行の政策を躊躇なく批判する原動力になっているんですね。同時に欧米の国家は国民の安全を守ると断言していますが、僕個人はそれはロマティックな幻想に過ぎないと感じました。著者は次のような体験から欧米人に対する強烈な劣等感を抱いたのかもしれないですね。
あるとき、ポルシェのスポーツカーから長靴を履いた男が颯爽と降り立つところを見て、「いつか同じことをしてみたい」と思いました。
1940年体制という史観
戦後の体制はすでに戦中に確立されていたというのが著者の独特な史観であると思います。これが本書の真髄にあたる考え方です。それは官僚によって、しかも人事を政治に掌握されない大蔵省の官僚を中心に形成された、と。
著者はGHQすら官僚に操作されていたと主張しています。
官僚機構が占領政策の最中にそこまでの自己保存能力を有していたのかは非常に疑問ですが、案外占領政策で派遣された米国の人材は行政の素人が多かったのかもしれません。操るのは容易だったと推測されます。
この体制はバブルの崩壊とともに終焉を迎えたと著者は主張します。
豊かになるには、働く必要がある?
著者は金融政策による円安の迎合や国の保護、大企業の雇用に依存するのではなく、産業構造の転換によって生産性を高め、真面目に働くことが日本の生き残る道だと説きます。でも、きっと産業構造の転換は破壊による不可抗力(戦争や壊滅的な大災害)なくしては起こり得ないのでは?とも思うのです。
組織を横断した(はみ出した)人間はやはり面白いことがわかりました。
著者のように、東大工学部に在籍しながら、経済学を独学で習得し(後年YaleでPhD.を取得する)、大蔵省の官僚でありながら、アカデミズム(大学)に出向するというスピンアウト経験は縦社会のルートを是とする日本の組織にあって、かなり特殊だと思うのですが、僕はとても面白いなと思うのです。
だからこそ、もうこの本は回顧録として出版すべきだったと思います。日本の経済史を全面に出さなくとも著者の人生だけでも十分主役を張れるのですから。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。


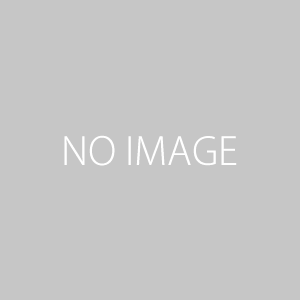
この記事へのコメントはありません。